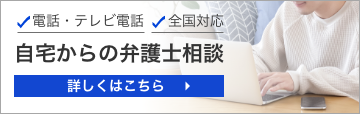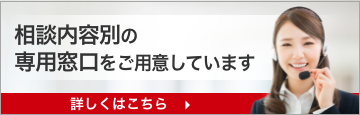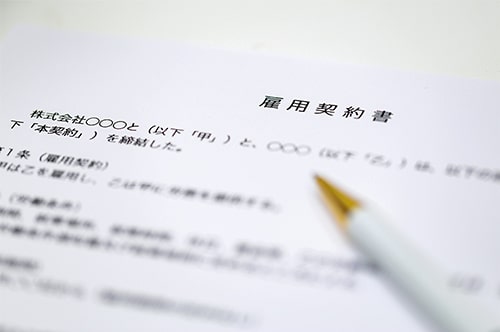人員整理で解雇する方法は? 要件や退職させるリスクを弁護士が解説
- 労働問題
- 人員整理
- 解雇

令和5年度、山形県内の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争は2138件で、そのうち解雇に関するものは272件でした。
企業が人員整理を行うにあたり、整理解雇は最終手段となります。ただし、安易に整理解雇を行えば違法と判断される可能性が高いので、要件を満たすかどうか、よく検討をすべきでしょう。
本記事では、人員整理の目的で行う整理解雇の要件や手続き、注意点などを、ベリーベスト法律事務所 山形オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和5年度個別労働紛争解決制度の運用状況」(山形労働局)
1、人員整理による解雇とは?
企業が業績不振に陥った場合は、人員整理を検討すべきです。ただし、企業側が従業員を一方的に解雇することは最終手段であり、安易に解雇を行うべきではありません。
-
(1)人員整理とは
「人員整理」とは、会社都合によって従業員を退職させて、その数を減らすことをいいます。経営不振などが原因で、人件費を減らすために人員整理が行われることがあります。
-
(2)整理解雇は人員整理の最終手段
人員整理の方法としては、以下の例が挙げられます。
- 希望退職者の募集
- 退職勧奨(=従業員に対して個別に退職を勧めること)
- 出向
- 転籍
- 解雇
このうち解雇は、企業側が一方的に雇用契約を解除し、強制的に従業員を退職させるものです。
解雇には「懲戒解雇」「整理解雇」「普通解雇」の3種類がありますが、人員整理を目的とする解雇は整理解雇に当たります。
整理解雇された従業員は、仕事と生活の糧を失ってしまいます。解雇前と同等の待遇での再就職が困難なケースも少なくありません。
従業員がこのような状況に陥らないように、整理解雇は法律で厳しく制限されています。
そのため、整理解雇はあくまでも最終手段と位置付けて、まずは別の方法による人員整理を試みてください。 -
(3)整理解雇のメリットとデメリット
整理解雇には、以下に挙げるようにメリットもデメリットもあります。両者を総合的に比較したうえで、整理解雇を行うべきか否かを適切に判断しましょう。
整理解雇のメリット
- 従業員の意向にかかわらず、強力に人員整理を進められる
- 残った従業員の負担が増える
- 今後も整理解雇が行われるのではないかと懸念した従業員が、転職を検討するおそれがある
- 整理解雇をしないことが要件とされている、会社への助成金の支給が打ち切られる
- 従業員により、不当解雇として訴えられることがある
先述のとおり、整理解雇は厳しく制限されています。それ以外にも、残った従業員への業務の負担、精神的な不安を与えることになるため、慎重に進めるべきです。
2、整理解雇の4要件と解雇できないケース
整理解雇の有効性は、以下の4要件を総合的に考慮して判断されます。ただし、4要件を満たしている場合でも、解雇禁止に該当する場合は整理解雇を行うことができません。
-
(1)整理解雇の4要件
整理解雇の有効性は、以下の4要件を総合的に考慮して判断されます。
① 人員削減の必要性
企業が倒産の危機に瀕している場合には、人員削減の必要性が認められます。
また、債務超過や赤字累積など、高度の経営上の困難が生じている場合にも、人員削減の必要性が認められる余地があります。
② 解雇回避努力義務の履行
整理解雇を避けるため、できる限りの努力を尽くしたことが必要です。具体的には、以下のような取り組みが求められます。
- 労働時間の短縮、残業の削減
- 出向
- 新規採用の抑制、中止
- 希望退職者の募集
- 役員報酬の削減
- 会社資産の売却
- 助成金の申請
③ 被解雇者選定の合理性
整理解雇をする従業員は、合理的かつ公平な基準を適切に運用して選定しなければなりません。
たとえば、以下のような選定基準を設けたうえで、複数人が意見を出し合って対象者を選ぶなどの取り組みが求められます。
- 年齢
- 勤続年数
- 勤怠(欠勤、遅刻、早退など)
- 勤務成績
- 配置転換の難しさ
- 解雇による生活への影響
④ 解雇手続きの妥当性
整理解雇がやむを得ない事情であることを、労働者側に対して十分に説明することが求められます。対象者に加えて、労働組合がある場合は労働組合にも説明を行うべきです。
ただし、単に1回説明しただけでは、解雇手続きの妥当性は認められないと考えられます。複数回にわたって説明会を開催し、不服がある従業員とは対話の機会を設けるなどの対応をすべきでしょう。 -
(2)整理解雇が禁止されているケース
労働基準法などの法律では、一定の条件下において、企業による従業員の解雇を禁止しています。
たとえば以下のような状況にある場合は、整理解雇の4要件を満たしているとしても、整理解雇を行うことはできません(労働基準法第19条)。- 従業員が業務上の疾病によって休業している場合、または当該休業から復帰してから30日以内である場合
- 従業員が産前産後休業を取得している場合、または産前産後休業から復帰してから30日以内である場合
また、以下のような理由による整理解雇も禁止されています。もっとも、これらの理由による整理解雇は、4要件のひとつである「被解雇者選定の合理性」を満たさないと考えられます。
- 従業員の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
- 労働基準監督署への申告を行ったことを理由とする解雇(同法第104条第2項)
- 労働組合員であることなどを理由とする解雇(労働組合法第7条第1号)
- 労働委員会に対して不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇(同条第4号)
- 婚姻、妊娠、出産、産前産後休業の取得などを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第9条第2項、第3項)
- 育児休業または介護休業の申し出、取得を理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、第16条)
お問い合わせください。
3、不当解雇をすると訴訟のリスク大|整理解雇の手続きの流れと注意点
先述のとおり、十分な検討を行わないまま安易に従業員を整理解雇すると、不当解雇として解雇が無効と判断されるおそれがあります。さらに従業員に労働審判や訴訟を起こされ、深刻なトラブルに発展することになりかねません。
整理解雇を行う際には、次に紹介する手順と注意点を十分に踏まえたうえで、慎重に検討と手続きを行いましょう。自社だけで判断すると大きなリスクが懸念されるため、弁護士への相談をおすすめします。
4要件のひとつである「解雇回避努力義務の履行」を満たすため、あらかじめ役員報酬の削減などによるコストカットや、希望退職者の募集、退職勧奨などによる人員整理を行いましょう。
② 整理解雇の計画を立てる
やむを得ず整理解雇を行うことにした場合は、以下の事項を含む計画を立てましょう。
- 削減する人件費の額
- 対象とする部署や従業員の範囲
- 対象とする従業員の人数
- 整理解雇を行う時期
③ 選定基準を定め、整理解雇する従業員を選定する
4要件のひとつである「被解雇者選定の合理性」を意識しつつ、合理的かつ公平な基準を定めたうえで、整理解雇する従業員を選びます。
対象者の人選は、中立的な判断ができるメンバーで組織された合議体で行うことが望ましいです。
④ 労働者側に対する説明を尽くす
4要件のひとつである「解雇手続きの妥当性」を満たすため、対象者本人や労働組合に対して、整理解雇の必要性などを説明する機会を設けましょう。1回限りではなく、複数回にわたって説明を行うべきです。
⑤ 解雇予告または解雇予告手当の支払いを行う
一部の例外を除き、解雇日の30日以上前に解雇を予告するか、または解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告または解雇予告手当の支払い義務を怠ると、労働基準監督署の是正勧告や刑事罰の対象となるのでご注意ください。
⑥ 解雇する
事前に予告した解雇日が到来すると、その日をもって従業員を解雇したことになります。30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払った場合は、即日解雇も可能です。
解雇に伴い、雇用保険や社会保険に関する手続きを忘れずに行いましょう。
4、整理解雇の検討にあたって、弁護士へ相談するメリット
整理解雇の実施にあたっては、慎重な検討が求められます。弁護士に相談して、万全の体制を整えたうえで整理解雇に踏み切りましょう。
整理解雇の検討にあたって、弁護士に相談することには主に以下のようなメリットがあります。
- 検討すべき事柄を漏れなくリストアップできる
- 解雇の手順が法的に問題ないかを確認できる
- 退職者との間でトラブルが生じた場合でも、交渉や裁判手続きの対応を引き続き依頼できる
弁護士と協力して対応すれば、整理解雇に伴うトラブルに備えることができます。経営不振を理由に人員整理を行う際、整理解雇を実施せざるを得なくなりそうなら、早い段階で弁護士にご相談ください。
5、まとめ
人員整理を行うにあたり、整理解雇はあくまでも最終手段です。整理解雇を進める前に、まずは希望退職者の募集や退職勧奨などの代替手段を講じ、従業員とのトラブルを回避しましょう。
整理解雇がやむを得ない場合は、要件を満たしているかどうか慎重に検討するため、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、整理解雇に関する企業のご相談を随時受け付けております。経験豊かな弁護士が企業の実情に合わせてアドバイスいたしますので、早い段階でベリーベスト法律事務所 山形オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています