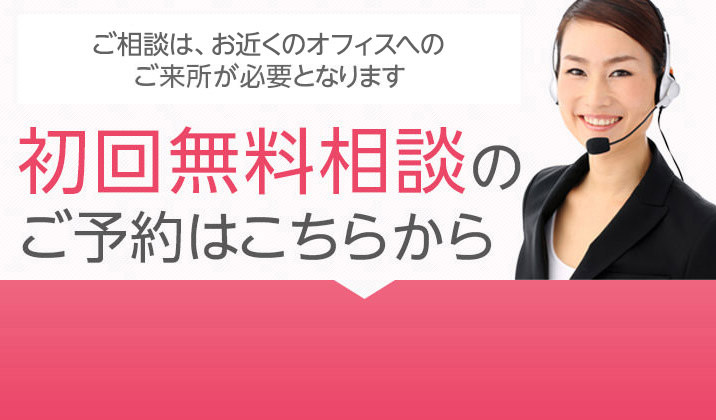離婚後も妻が居座る! 立ち退きさせる方法や居住権について解説
- 離婚
- 離婚
- 妻
- 居座る

離婚後も元妻が家に居座ってしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
とくに住宅ローンが残っている場合や家賃の支払いが滞っている場合、経済的な負担は大きくなってしまいます。
本コラムでは、居住権の考え方や離婚後も元妻が居座る場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 山形オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚後も居座る妻を退去させたい! ポイントは居住権
離婚後に元妻が自宅に居座り続ける場合、まず確認すべきなのが「居住権」です。しかし、居住権とは具体的にどのような権利を指すのでしょうか。
以下では、居住権に関する基本的な考え方や、離婚後に居座る元妻への対応を検討する上で押さえておきたいポイントを解説します。
-
(1)居住権とは?
居住権とは、一定の物件に継続して居住する権利です。法令上の用語ではありませんが、一般的な概念として広く認識されています。
持ち家や賃貸物件の場合、夫名義で所有・契約しているケースが多いため、離婚時に妻側から居住権を主張されることがあります。
離婚後に居座り続けている元妻を退去させたい場合には、「自宅の所有権(登記名義・契約名義)」が誰にあるかがポイントです。また、自宅が「持ち家」か「賃貸」かによっても、対応方法が異なります。 -
(2)共有財産の場合は一方的に退去させるのは難しい
結婚後に購入した自宅であれば、たとえ住宅の登記が夫の名義であったとしても、通常は夫婦の「共有財産」として扱われます。
そのため、まずは財産分与や居住に関する条件について話し合い、離婚後の自宅の扱いを明確にする必要があります。
財産分与が成立していなければ、自宅の処分や使用は夫婦の共有であるとみなされ、一方的に退去を求めることはできません。
なお、結婚前に夫名義で購入した、もしくは夫側の両親から贈与された自宅であれば、夫の特有財産として扱われるのが一般的です。自宅が夫の特有財産である場合、離婚後は元妻に対して退去を要求できます。 -
(3)元妻が家賃を支払わない場合は滞納分を請求できる可能性がある
自宅が賃貸物件で、元妻が家賃を支払っていない状況であれば、元妻に対して滞納分を請求できる可能性があります。
滞納分を請求したい場合は、以下の点を確認しておきましょう。① 賃貸契約の名義人は誰か
② 元妻が連帯保証人になっていないか①の賃貸契約が夫名義で、元妻が住んでいるにもかかわらず家賃を支払っていない場合、滞納分は夫に対して請求されます。しかし、②で元妻が連帯保証人であれば連帯責任が発生するため、夫は元妻に滞納分を請求する権利があります。
実際に請求する際は住居の使用実態・支払履歴などの記録をしっかり残した上で、弁護士に相談しながら手続きを進めることが望ましいでしょう。
2、離婚後も居座る妻を立ち退かせる方法
離婚して財産分与が済んだにもかかわらず元妻が自宅に居座っている場合は、立ち退かせる方法を検討しましょう。関係性の悪化や問題の長期化を防ぐためには、状況に応じて段階的に対応する必要があります。
元妻に退去を求める具体的な方法は、以下のとおりです。
-
(1)任意で交渉を進める
もっとも穏便に立ち退かせる方法は、任意の交渉です。建物明渡請求訴訟を行う場合は1年以上の期間がかかる場合もあるため、まずは話し合いでの解決を試みましょう。
交渉する際は感情的にならず、冷静に退去してほしい旨を伝えます。元妻が了承した場合は退去期限を設定し、期日までに立ち退いてもらいましょう。
後々のトラブルを防ぐためにも、交渉の内容は記録して残しておくことが望ましいです。 -
(2)内容証明郵便を送付する
任意の交渉がうまくいかない場合には、内容証明郵便の送付を検討しましょう。内容証明郵便とは、誰が・いつ・どのような内容を相手に送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
「正式な意思表示」であることを明確に示せる内容証明郵便には、相手に心理的なプレッシャーを与える効果があります。法的効力をもつわけではありませんが、後に証拠としても活用できるため、退去要求を行う際の有効な手段です。 -
(3)調停調書に離婚後の妻の居住について記載がない場合は民事訴訟を行う
調停調書に妻の居住に関する記載がない場合は、明け渡しを求める民事訴訟を提起する方法があります。
調停調書とは、調停が成立した際に作成される書面です。家庭裁判所での離婚調停手続きを経て離婚すると、夫婦間で合意した内容は調停調書に記載されます。
内容証明郵便を送付してもなお居座り続け、調停でも居住の取り決めをしていない場合は民事訴訟の提起を検討しましょう。「建物明渡請求訴訟」を提起することで、権利のない者に対して明け渡しを要求できます。
訴訟では、証拠集めや法的根拠に基づいた主張が求められます。個人で手続きを行うのは困難なため、弁護士に相談しながら進めましょう。 -
(4)調停調書に記載がある場合は強制執行を申し立てる
調停調書に退去に関する記載がある場合や、訴訟で明け渡し請求が認められた場合には、強制執行の申し立てができます。
建物明け渡しにおける強制執行とは、裁判所の執行官が対象者を強制的に退去させる手続きです。退去を命じられたにもかかわらず元妻が居座り続けている場合は、最終手段として検討しましょう。
なお、強制執行の申し立てには調停調書や判決正本などの債務名義のほか、執行文の付与や送達証明書の取得が必要です。強制執行ができるかどうか、またどのタイミングで行うべきか悩んだらまずは弁護士へ相談することをおすすめします。 -
(5)弁護士に相談する
弁護士に相談することも、元妻を立ち退かせる方法として有効な手段です。
弁護士は、状況に応じて最適な退去要求の方法をアドバイスします。また、交渉の代行や書面作成・法的手続きまで総合的なサポートを受けることも可能です。
とくに元妻と感情的な対立がある場合や法的主張をされた場合には、早めに弁護士に相談することでスムーズな解決が期待できるでしょう。
お問い合わせください。
3、元配偶者へ退去を促す前に確認したいこと
自宅に居座る元配偶者に退去を求める際は、まず自身の状況を整理し、リスクを回避するための準備を行いましょう。退去を促す前に確認しておきたい3つのポイントを、以下で具体的に解説していきます。
-
(1)離婚時に財産分与や慰謝料などの条件を決めておく
離婚時には、財産分与や慰謝料などとあわせて自宅の退去に関する条件も決めておきましょう。条件が決まらないまま離婚を進めると、退去の要求が困難になる可能性があるためです。
たとえば、不動産の名義人ではない配偶者の退去日や、退去するまでの賃料・光熱費・食費の負担などの条件を決定します。
離婚時は、夫婦間の話し合いや条件の取り決めが非常に大切です。合意した内容は離婚協議書などの書面で残すことで、後々トラブルになるリスクを軽減できます。 -
(2)感情的に追い出そうとしない
居座っている元妻に不満を感じたとしても、感情的に追い出すのは避けましょう。暴言や威圧的な言動・行動は、相手に精神的苦痛を与えたと判断され、慰謝料請求の原因になってしまうおそれがあります。
不利な立場になるリスクを軽減するためには、法的手続きを前提とした冷静な対応が重要となります。
当事者だけでの話し合いが難しい場合は、弁護士などの第三者を介入させることも検討しましょう。 -
(3)住宅ローンが残っている場合は支払いについて協議しなければならない
住宅ローンが残っている場合、支払いについても協議しなければなりません。
自宅に関しては、現在の価値よりもローン残高のほうが上回っている「オーバーローン」の状態になっているケースも多いでしょう。財産分与はプラスの財産を分ける制度であり、オーバーローンは負債であるため折半して分けることはできません。
したがって、離婚後にどちらがローンの残債を支払っていくかを決定する必要があります。住宅ローンの支払いはトラブルになりやすい問題のため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
4、離婚後も妻が居座る場合は弁護士に相談を
元妻が離婚後も自宅に居座り続けている場合、自己判断だけでは解決が難しいケースもあります。このような場合には、弁護士への相談を検討してみてください。
以下では、弁護士に相談することで得られる3つのメリットを解説していきます。
-
(1)相手との交渉を代行できる
弁護士は、相手との交渉を代行できます。離婚後も元妻と顔をあわせることに、ストレスを感じる方も多いでしょう。
とくに居住や財産分与に関する話し合いは感情的な問題が発生しやすく、冷静な対応が難しくなる傾向があります。弁護士に依頼すればすべての交渉を任せられるため、直接やり取りする必要はありません。
第三者である弁護士が入ることで、精神的な負担が軽減され、交渉がスムーズに進む可能性も高まるでしょう。 -
(2)法的に効力のある合意書を作成できる
法的に効力のある合意書を作成できる点も、弁護士に相談するメリットのひとつです。
居住に関する話し合いで合意が成立しても、口頭の約束だけでは後から覆されてしまう可能性があります。たとえば、「いつまでに退去する」と合意していたにもかかわらず、「そんな約束はしていない」と言われてしまうケースなどです。
こういった問題を防ぐためには、取り決めた内容をまとめた合意書の作成が有効です。弁護士であれば、法的に有効な合意書を作成するサポートができます。 -
(3)裁判に発展した場合、法的な手続きをサポートできる
弁護士は、裁判に発展した場合の法的手続きもサポートできます。
離婚後の居座り問題では話し合いでの解決が難しく、最終的に裁判に発展するケースもあるでしょう。しかし、裁判手続きは複雑で、ひとりで行おうとすると多くの時間と労力がかかってしまいます。
弁護士に依頼すれば、必要書類の準備から裁判所での手続き・出廷まですべてを任せられます。また、戦略的かつ的確に手続きを進められるため、不利な状況になるリスクを下げることができるでしょう。
5、まとめ
離婚後に居座り続ける元妻を退去させたい場合、自宅の所有権が誰にあるかによって対応方法が変わってきます。また、自宅が「持ち家」か「賃貸」かでも取るべき対応は異なります。
いずれの場合でも、感情的に追い出そうとするのではなく、冷静に対応することが重要です。
どのように対処すればいいかわからないときは、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士のサポートを受けることで、問題解決への道筋が見えやすくなり、精神的な負担も軽減されるでしょう。
離婚後の条件や居住問題で悩んだ際は、お気軽にベリーベスト法律事務所 山形オフィスの弁護士へご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています