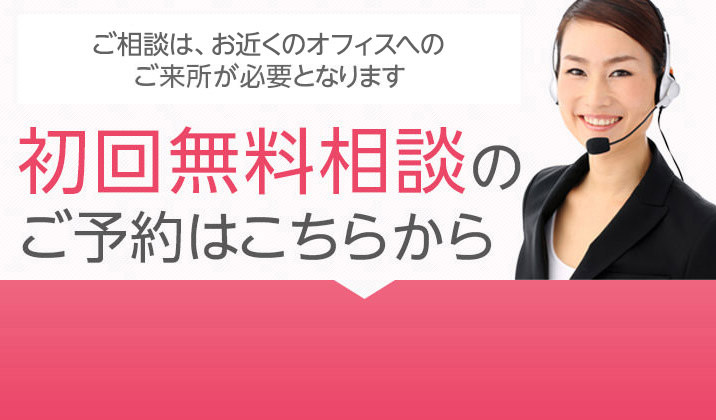離婚調停で円満に解決できる? 使える制度と話し合う内容、進め方
- 離婚
- 離婚調停
- 円満

離婚をしたくても夫婦の話し合いでは離婚の合意に至らないという場合は、家庭裁判所の離婚調停を利用することができます。
裁判所が公表している司法統計によると、令和5年に山形家庭裁判所に申し立てられた婚姻中の夫婦間の事件に関する調停は、290件でした。
離婚には円満に解決するためのポイントがあります。本コラムでは、離婚時に利用できる裁判所の制度と円満に離婚を目指す方法について、ベリーベスト法律事務所 山形オフィスの弁護士が解説します。協議離婚や調停離婚に臨むときは、このコラムで紹介するポイントを押さえた対応を検討してください。


1、離婚時に利用できる裁判所の制度
離婚時に利用できる裁判所の制度としては、主に以下の3つの制度があります。
-
(1)夫婦関係調整調停(離婚)|離婚調停
夫婦関係調整調停(離婚)とは、一般的に「離婚調停」と呼ばれるものを指します。
離婚調停は、離婚を希望する夫婦が家庭裁判所において調停委員を交えて話し合いを行う手続きです。夫婦の話し合いによる協議離婚では離婚の合意に至らなかったときに、離婚調停が利用されます。
なお、夫婦の離婚問題については、調停前置主義が適用されます。したがって、相手が行方不明など特段の事情がない限りは原則として離婚訴訟を提起する前提として、離婚調停を経ていなければなりません。 -
(2)夫婦関係調整調停(円満)|円満調停
夫婦関係調整調停(円満)とは、一般的に「円満調停」と呼ばれています。
円満調停は、夫婦関係の修復を希望する夫婦が家庭裁判所において調停委員を交えて話し合いを行う手続きです。夫婦だけでは関係改善が難しい場合に、関係修復の話し合いの場として円満調停が利用されます。 -
(3)婚姻費用分担請求調停
婚姻費用分担請求調停とは、婚姻費用の分担について夫婦の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停を利用して取り決めを行う手続きです。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要になる費用をいい、衣食住の費用のほか、医療費、教育費、交際費などが含まれます。主に、離婚前に別居をすることになった夫婦が別居中の生活費の支払いに関する事項を取り決めるために利用されます。 -
(4)子の監護者の指定調停
子の監護者の指定調停とは、離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で、どちらが子どもを監護するのか争いがある場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して監護者の取り決めを行う手続きです。
子どもがいる夫婦が別居をすることになった場合、どちらが子どもと一緒に生活するのかで揉めることがあります。当事者同士の話し合いで子の監護者が決まらないときは、子の監護者の指定調停が利用されます。
2、離婚時に話し合いで決めること
離婚時に話し合いで決めるべき事項としては、以下のようなものがあります。
-
(1)親権者
夫婦に子どもがいる場合は、父または母のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
基本的には夫婦の話し合いにより親権者を決めることになりますが、話し合いがまとまらないときは離婚調停の申立てを行い、調停手続きの中で親権者についても話し合いをしていきます。 -
(2)養育費
親権者として子どもと一緒に生活する親(監護親)は、子どもと同居しない親(非監護親)に対して、養育費を請求することができます。
養育費の金額や支払期間、支払い方法などは夫婦の話し合いにより決めることになりますが、話し合いがまとまらないときは離婚調停の中で取り決めていきます。 -
(3)慰謝料
配偶者が離婚に至る原因を作るなど有責性が認められる場合は、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料を請求できる主な原因としては、不倫、DV、モラハラ、悪意の遺棄などが挙げられます。
有責配偶者に対して慰謝料を請求しても、簡単には自らの非を認めませんので、配偶者の有責性を立証するための証拠を集めることが重要です。 -
(4)財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を離婚時に清算する制度です。
婚姻期間が長くなればなるほど夫婦の共有財産は多くなりますので、離婚後の経済的な不安を解消するためにも、適正な財産分与を実現することが大切です。
なお、財産分与の割合は、夫婦の貢献度により決められますので、原則として2分の1の割合になります。これは、妻が専業主婦であったとしても変わりありません。 -
(5)面会交流
離婚して子どもと別々に暮らすことになる非監護親はが子どもとの定期的・継続的に交流すること、これを面会交流といいます。
子どもにとっても、自らの親と会って交流することは非常に重要な意味を持ちます。また、親権を持たない親としては、離婚後も子どもの成長を近くで見守りたいとお考えになるのではないでしょうか。夫婦としてうまく生活できなかったとしても、子どものために面会交流の内容を検討し、双方のルールを決めておくことが望ましいでしょう。 -
(6)年金分割
年金分割とは、離婚する際に、夫婦が結婚していた期間に納付されていた厚生年金の保険料を分けあい、それぞれを自分の年金額に反映させる制度です。
たとえば、夫が会社員で厚生年金を納付しており、専業主婦の妻が夫の扶養に入っていた場合、妻は国民年金の第三号被保険者として記録されています。この場合、妻が受け取れる年金は老齢基礎年金(国民年金分)のみを受給できます。
つまり、離婚してそのまま手続きをしなければ、妻は厚生年金分を受け取ることができません。しかし、婚姻中、夫が働くために家庭を支えていた妻が、離婚したからといって婚姻中に納付されていた厚生年金分を受け取れないのは不公平です。そのため、婚姻期間中に払われていた厚生年金の記録を分割するよう請求できるようになっているのです。
なお、年金分割を請求期限は、離婚した翌日から数えて2年以内というルールがあります。この期間を過ぎてしまうと、年金分割が認められない可能性があるため、離婚が決まったら速やかに手続きすることをおすすめします。
3、円満に離婚を目指す方法はある?
円満に離婚を目指すのであれば、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
-
(1)感情的にならずに落ち着いて話をする
円満に離婚をするには、感情的にならずに落ち着いて相手と話をすることが大切です。水掛け論などにならないためにも、あらかじめ、財産分与に必要な通帳のコピーなどの書類を集めておくことも重要です。感情的になって相手を批判しだすとお互いの関係性が悪化してしまい、円満に離婚するのが難しくなってしまいます。
離婚の話し合いという性質上、どうしても感情的になってしまいがちですが、冷静になって資料を集めたうえで、話し合いを行うようにしましょう。 -
(2)自分の主張だけでなく相手の意見にも耳を傾ける
円満に離婚するには、お互いが納得して離婚に至ることが重要です。
それには、自分の意見ばかり主張するのではなく、相手の意見にも耳を傾けなければなりません。有利な条件で離婚をしたいという気持ちも十分に理解できますが、円満な離婚を重視するのであれば、多少の譲歩も必要になります。相手の意見も尊重しながら話し合いを進めていくようにしましょう。 -
(3)焦らずに時間をかけて話をする
すぐに離婚をしたいという気持ちもわかりますが、円満に離婚するには焦らず時間をかけて話をすることが大切です。
離婚は、夫婦二人にとって重要な人生のイベントになります。お互いが納得できるまで話し合って出した結論であれば、後悔も少ないはずです。焦って離婚をしてしまうと、後々まで不満を引きずることになり、お互いにわだかまりが残ってしまうこともありますので注意が必要です。 -
(4)冷静な話し合いができるタイミングや場所を選ぶ
円満に離婚をするには、離婚の話し合いをするタイミングや場所も重要になります。
夫婦に子どもがいる場合には、子どもを実家に預けてから離婚の話し合いをする、平日は仕事で忙しいようであれば、ゆっくり話し合いができる休日に離婚の話し合いをするなどお互いが落ち着いて話し合いができるタイミングや場所を選択するようにしましょう。
4、弁護士に対応を依頼すべきケース
以下のようなケースについては、弁護士に対応を依頼した方がよいでしょう。
-
(1)相手が話し合いに応じないケース
離婚をしたいと伝えても相手が話し合いに応じてくれないようなケースでは、それ以上離婚に関する話し合いを進めることができません。これではいつまでたっても離婚することができませんので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士に依頼すれば代理人として相手と交渉してもらうことができますので、相手も弁護士が窓口になれば、話し合いに応じてくれる可能性があります。 -
(2)離婚条件で争いがあるケース
夫婦が離婚する際には、さまざまな離婚条件の取り決めが必要になります。お互いが希望する離婚条件に隔たりがあるようであれば、当事者同士の話し合いでは解決は困難ですので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士であれば、離婚条件の取り決め方や相場を把握していますので、適正な離婚条件を提案することができます。離婚条件に争いがあるケースでも弁護士から法的根拠に基づいて、こちらが提示する離婚条件の正当性を説明すれば、相手も納得してくれる可能性が高くなります。 -
(3)調停や裁判などの法的対応が必要になるケース
夫婦の話し合いでは解決が難しいケースについては、離婚調停や離婚裁判などの法的対応が必要になってきます。このような法的対応を自分だけで対応するのが不安だという方は、弁護士に依頼したよいでしょう。
依頼を受けた弁護士は調停期日に同席することが可能です。初めての調停でも不安なく臨むことができるでしょう。また、訴訟にまで発展したとしても、すべての対応を弁護士に任せることができますので、ご自身の負担を大幅に軽減することが可能です。
お問い合わせください。
5、まとめ
夫婦が円満に離婚するためには、感情的にならず冷静に話をする、相手の意見にも耳を傾ける、タイミングや場所に配慮するなどいくつかのポイントがあります。これらを踏まえて話し合いをすれば円満に離婚できる可能性が高くなりますが、それでも離婚の合意がまとまらないときは、専門家である弁護士に対応を委ねるとよいでしょう。
円満な離婚を希望される方や、離婚したいもののどのように進めればわからないときは、離婚問題についての知見が豊富な弁護士が所属するベリーベスト法律事務所 山形オフィスまでお気軽にご相談ください。親身になって対応します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています