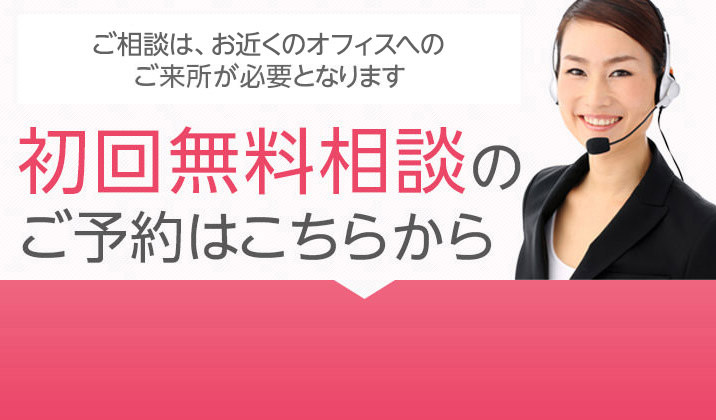離婚で話し合うことは? 話し合いで決めるべきこととポイント
- 離婚
- 離婚
- 話し合うこと

厚生労働省が公表している「令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況」によれば、同年の山形県の婚姻件数は3184件であるのに対して、離婚件数は1197件にのぼります。
これから離婚をしようとする際、“なにを話し合うべきか”を知っておくことはとても大切です。今後の生活や子どもの養育などについて、適切に取り決めておかなければ、後々困ってしまう可能性もあります。
そこで、この記事では、離婚する際に話し合うことや、離婚の話し合いをするときのポイント、話し合いがまとまらない場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 山形オフィスの弁護士が解説していきます。


1、離婚する際に話し合うことは?
夫婦が離婚する際には、以下のような項目を話し合う必要があります。
それぞれについて解説していきます。
-
(1)離婚に合意するかどうか
まずは、お互いが離婚することに合意するかを確認しましょう。
夫婦で話し合う「協議離婚」、裁判所を介して話し合う「調停離婚」の場合には、夫婦双方が離婚に合意しなければ、手続きを進めていくことはできません。相手が離婚に合意しない場合は、強制的に離婚を成立させるために、裁判所に訴訟を提起して「裁判離婚」を提起することになります。
夫婦双方が離婚に合意する場合には、次のような各種離婚条件について調整していきます。 -
(2)子のこと(親権者、養育費及び面会交流に関する事項等)
① 親権者
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、どちらか一方を親権者と指定する必要があります。親権者が決まらないと、役所は離婚届を受理してくれません。
② 養育費
親権者ではなくなった親(非監護親)でも、未成年の子どもの扶養義務は残ります。したがって、子どもと離れて暮らす親は、親権者となる親に養育費を支払う義務があります。
養育費は、月々の支払金額、支払い方法、支払期限などについて話し合って決める必要があります。
③ 面会交流
面会交流とは、非監護親と子が、直接会って一緒に時間を過ごしたり、電話やメールなどで交流したりするための機会を設けることです。面会交流は、子どもと離れて暮らす親の権利であると同時に、子どもの心身の成長のために必要なものであるため、適切に取り決めておく必要があります。
具体的には、面会交流の頻度、交流の方法、子の受け渡し方法、父母の連絡手段などについてあらかじめ決定しておくことが重要です。 -
(3)婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦や未成年の子どもが生活を営むために必要となる経費のことを指します。民法では、家族皆が同等の水準の生活を営めるよう、生活費として婚姻費用を分担する義務が定められています。
そのため、別居をしていたとしても離婚が成立するまでの間、相手に婚姻費用を請求することができます。
ただし、実務的には、請求時から離婚までが、費用を受け取れる期間とされています。別居する場合には、速やかに婚姻費用の分担について合意し、請求するようにしましょう。 -
(4)財産分与
夫婦が離婚する際には、財産分与についても取り決めておくことが大切です。
財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して取得した共有財産について、離婚の際に公平(原則2分の1ずつ)に分け合う制度のことです。
たとえば、結婚してから購入したマイホームや自動車、預貯金などについては、夫婦で公平に半分ずつ分け合うように請求することができます。妻が専業主婦だったり、不動産の名義人が夫だったりした場合でも、公平に財産分与を求める権利が認められています。 -
(5)年金分割
老後の生活のため、年金分割についても確認しておきましょう。
年金分割とは、結婚していたい期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができるという制度です。厚生年金の支給額の計算のベースとなる厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ当事者で分割されることになるため、将来年金を受け取る際に加算してもらえます。
なお、国民年金や、婚姻前に納付した厚生年金については分割の対象外です。 -
(6)慰謝料
相手が離婚の原因を作った「有責配偶者」である場合には、慰謝料を請求することができます。有責とされるのは、不貞行為や家庭内暴力(DV)、精神的虐待(モラハラ)などがある場合で、こうした不法行為を理由とした慰謝料の請求が求められます。
ただし、相手が任意に支払いに応じない場合には、調停や訴訟を起こして請求していく必要があります。
2、離婚の話し合いをするときのポイント
離婚は人生の大きな転換点であり、話し合いは慎重かつ冷静に進める必要があります。
ここでは、離婚を話し合う際に押さえておきたい4つのポイントを詳しく解説します。
-
(1)離婚を切り出す前に離婚後の生活設計をしておく
離婚は感情だけで決めるものではなく、その後の生活設計が重要です。
離婚後の生活を見据えた準備が不足すると、経済的や精神的に不安定な状況に陥る可能性があります。そのため、以下のような離婚後の生活設計をしておきましょう。
① 住居の確保
まず、離婚後、どこに住むのかを明確にします。持ち家に住み続けるのか、賃貸物件に引っ越すのかを考えましょう。
② 収入源
次に、離婚後の収入源や生活費の計算をしておきます。収入が不足する場合は、働き方を変える、資格を取るなどの対策が必要です。
③ 子の環境
さらに、子どもを監護養育する、養育費や学校生活への影響について考える必要があります。安定した環境を提供できるよう配慮する必要があります。 -
(2)譲れるものと譲れないものを明確にしておく
夫婦で離婚条件を話し合う場合には、譲れるものと譲れないものを明確にしておくことが重要です。
離婚協議をする際に、あなたが「一歩も引かないという姿勢」を固辞することは、得策とはいえません。このような場合には、話し合いが長期化してしまい、最終的には望んでいなかった離婚条件で離婚せざるを得なくなるというリスクもあります。
そのため、「絶対に譲れないもの(たとえば親権や養育費など)」と「妥協できるもの(たとえば財産分与や慰謝料など)」を整理し、柔軟に対応することがポイントです。 -
(3)感情的にならず冷静に話し合う
離婚は感情的な対立を生みやすいものです。
しかし、話し合いが感情的になると解決が遅れるばかりか、双方にとって不利益を招くこともあります。冷静に話し合うためには、弁護士や調停員などの中立的な第三者を交えて話し合いをすることです。
離婚協議の場は相手への怒りや不満をぶつける場ではなく、離婚条件について具体的な調整を図る場です。事前に紙に書き出して整理することも冷静に話し合うためには有効でしょう。 -
(4)証拠は話し合いの前に準備しておく
法的に有利な立場で話し合いを進めるためには、事前に証拠を収集しておくことが重要です。
離婚の際に重要となる証拠としては次のようなものがあります。- 不貞行為の証拠:写真、メッセージ、通話記録など
- 家庭内暴力(DV)や精神的虐待の証拠:医師の診断書、録音データ、警察への相談記録など
- 財産の証拠:銀行口座の明細、不動産登記簿、給与明細など
証拠の収集や整理は慎重に行う必要があります。強引・不当な手段で証拠を得ようとすると新たなトラブルに発展するリスクもあるため、弁護士に相談して進めるようにしましょう。
お問い合わせください。
3、話し合いがまとまらない場合の対処法とは?
夫婦間で離婚条件が決められない場合には、どうしたらいいのでしょうか。
ここでは、話し合いがまとまらない場合の対処法について解説していきます。
-
(1)第三者を交えて話し合う
当事者だけでの話し合いが難航する場合には、中立的な第三者を交えて話し合いをすることもひとつの手です。第三者に意見を聞いてもらい対立を防ぎながら、建設的な対話を行うことが期待できます。
親族や友人などにお願いすることもできますが、財産分与や養育費などの交渉が必要な場合は、弁護士を交えて話し合うと安心です。 -
(2)離婚調停を申し立てる
協議離婚が難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
調停手続きでは、調停委員会が夫婦の間に入って、話し合いを行うことになります。調停委員会は、家庭裁判所の裁判官1名と、一般市民の中から選ばれた調停委員2名によって構成されており、冷静な話し合いのサポートをしてくれます。 -
(3)弁護士に相談する
当事者だけの話し合いでは離婚できない場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。離婚問題の実績がある弁護士に対応を依頼することで、希望する条件で離婚ができる可能性が高まります。
また、適切なアドバイスを受けたり、相手方との交渉などを任せたりできるというメリットがあります。
お問い合わせください。
4、離婚問題を弁護士に相談すべき3つの理由
ここでは、離婚問題を弁護士に相談すべき3つの理由について解説していきます。
-
(1)適切な離婚条件についてアドバイスを受けられる
弁護士に相談することで、適切な離婚条件についてアドバイスを受けることができます。当事者だけの話し合いでは、専門的な知識が不足しているため、不利な離婚条件で合意してしまうケースも少なくありません。
弁護士に離婚を相談することで、財産分与の方法や、養育費、慰謝料などについて、法的に適切なアドバイスを受けることができます。 -
(2)相手との交渉を一任できる
相手方との交渉を一任できることも弁護士に依頼するメリットです。特に、感情的な衝突により問題が複雑になっているケースでは、弁護士が代理で交渉することでスムーズに調整が進む場合もあります。
弁護士に依頼しておけば、離婚する際に取り決めておくべき事項を「決め忘れていた」という事態も回避することができます。 -
(3)裁判に発展した場合であっても引き続き対応を任せられる
早い段階から弁護士に依頼することで、調停や訴訟に発展した場合も、引き続き裁判対応を任せることができます。裁判所に提出する訴状や書面、証拠の準備も含めて、依頼者の権利を実現できる適切な手続きが可能です。
裁判は専門的な知識と技術が求められるため、弁護士の力が大きな助けとなります。弁護士のサポートにより、裁判手続きの不安や負担を軽減し、適切な結果を得る可能性が高まります。
お問い合わせください。
5、まとめ
離婚する夫婦が話し合うことには、次のようなものがあります。
- 離婚に合意するかどうか
- 親権者の指定・養育費・面会交流
- 婚姻費用
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
ただし、話し合いの内容は夫婦によって異なります。不安な場合には、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題を弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができるだけでなく、相手との交渉や裁判対応をスムーズに進めることができます。弁護士は不利な条件を避け、公平かつ納得のいく解決を目指します。
ベリーベスト法律事務所 山形オフィスには、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍しております。離婚の交渉や手続きで悩まれたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています